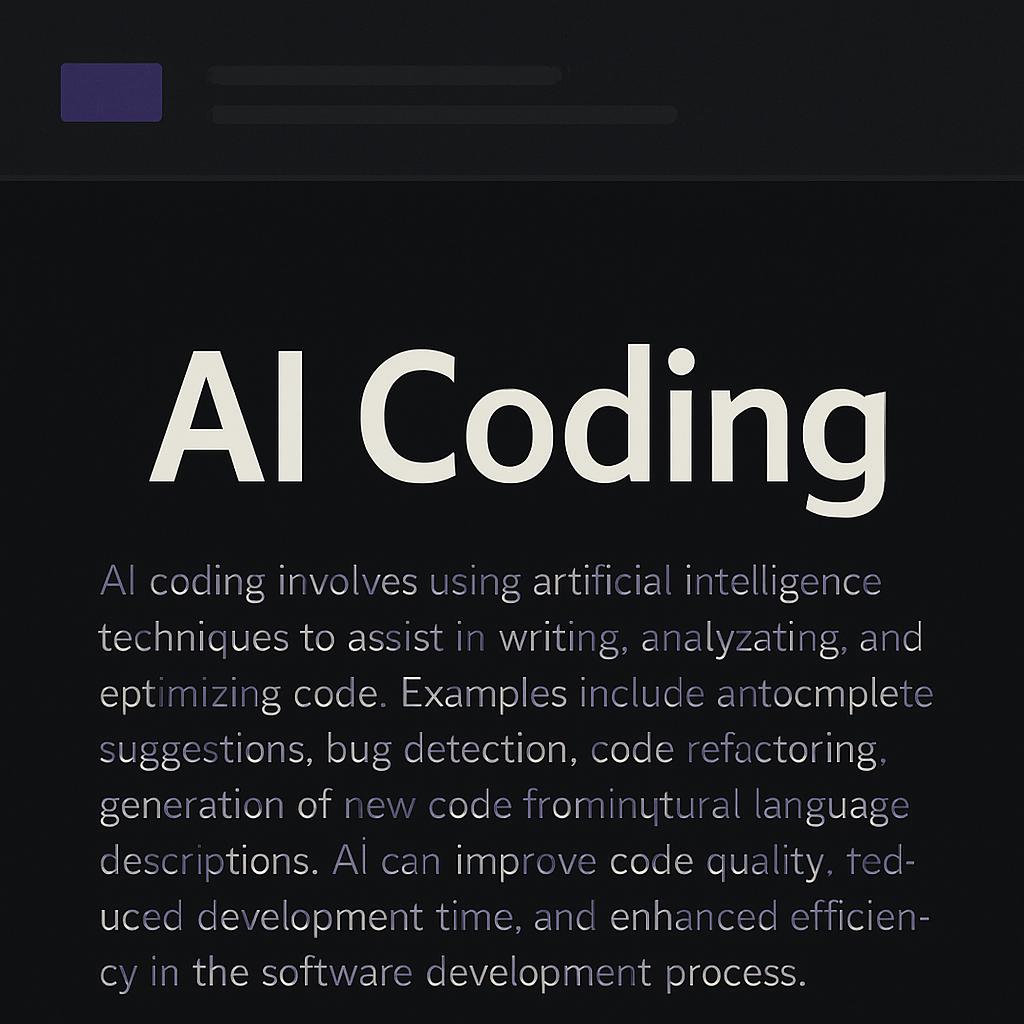業界の神、松本弁理士が、ご近所のスーパーでウイスキーを小分け販売しているのを発見されたとのことで、Xで話題になっています。
小分け販売は、商標の世界で昔からいわくつきの問題です。我が国の商標法では、小分け販売は、基本的にNGとする立場です。有名どころでは、ハイミー最高裁判例や、マグアンプK事件、HERSHEY’S事件、STP事件などがあります。
これらの事件では、大入りの業務用商品を買って、小分けにして袋などに商標を印刷して販売する行為が商標権侵害と言われることが多いです。単に小分け販売するだけでは権利侵害となりづらい点に注意が必要です。
過去事例に照らして、お酒の小分け販売は商標権侵害だと言ってしまっていいのでしょうか。
要するに、売り場でお酒の銘柄を値札などで表示などすることが、商標法上許されるのでしょうか。
例えば、スーパーでもコンビニでも、「いいちこ1000円」などと値札がついて、ボトルのまま売られています。これが商標権侵害とならないのは、常識でおわかりいただけると思います。
なぜかというと、その商品がいいちこであることを、お客さんの誰も疑わないからです。1000円だったら高いから買うのやめようということはあるかもしれませんが、「これほんとはいいちこじゃないかもしれないから怪しいので買うのやめよう」ということはないと思います。もし販売者が偽物のいいちこを売ったら、当然商標権侵害となります(※偽物を作った業者に責任を取らせるのが一般的です)。一方で、スーパーが、本物のいいちこを、「いいちこ」という商標を表示して販売することは違法ではありません。
このような、お客さんの「これは本物のいいちこだろう」という信用を保証することを、商標の世界では、出所表示機能といいます。「いいちこ」と値札に書いてあれば、それは三和酒類株式会社が作ったあの焼酎だと理解できる、そんな世界を保証しようというのが商標の役割のひとつです。
ではなぜ小分け販売が問題となるのでしょうか。
それは、商品の品質が保証されないからという説明がなされます。
小分け販売してしまうと、中身わからないですよね。安酒が混ざっているかもしれません。ワインなどの醸造酒は、酸化して味が変化します。ビールの炭酸が抜けてしまったら、もはや同じお酒とは言えないでしょう。
このように、「小分けにされて、実は安酒が混ぜられてるんじゃない?」「お酒の味(品質)が変わってるんじゃない?」というお客さんからの信用を保護するのを、品質保証機能といいます。これもまた、商標の基本的な機能のひとつで、裁判所は一貫してこれを認めています。
このように考えてみると、スーパーでのお酒の小売は、上記商標の基本的な2つの機能を害する可能性があり、リスクが高いように思います。
一方で、駄菓子屋で、もともと小袋に入っているお菓子(例えば、キットカットやパイの実など)を1個単位で販売することが商標権侵害になってしまうかというと、それはまた別の議論です。もともと小分けされているんだから、バラで売っても品質は変わらない(品質保証機能は害されない)とも考えられるからです。
日本では、商標の品質保証機能がそれほど重視されているとは言えないのが現状ですが、やはり製造業者が保証したい品質を流通業者が低下させることを許さないというのが、商標法の立場だといえます。
販売者におかれては、安易に小分けやバラ売りをすることは避けたほうが無難かもしれません。